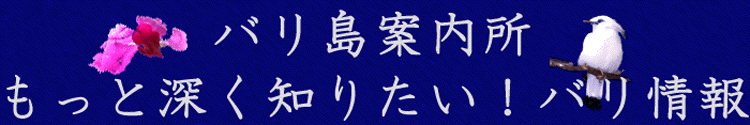
バリ島完全個人旅行。あれこれ知りたいニッチな情報サイト |ホーム|リンク| |
|
| バリ島 初心者入門 | バリ島の生活文化を深く知りたい! | |
|
|
バリ島 ヒンドゥー教が生活の中にあることってどうですか? |
|
| |
|
バリ島に訪れると、多かれ少なかれ、どなたでもバリのヒンドゥー教の慣習に必ず触れることになります。 道を歩けばチャナンという神様へのお供え物が至る場所に置いてある。 時には踏んづけてしまうことも。 お寺の見学に行けば、もちろん肌の露出をしたまま入ることはできず、 素足でショートパンツ等を履いていると、大きな布であるサロンを腰から巻く必要がある。 車で道を進めば、途中でセレモニーの最中で伝統的衣装を身にまとった集団に出会う。 などなど。。。  私がバリ島でこの10年の間に肌で感じている、 バリ島のヒンドゥー教の慣習とバリ人の特性との関係について触れてみたいと思います。 なぜかといと、バリ人って一体なんなんだ!? ということが、私の意識の中に良い意味、悪い意味の両方で日々訪れてくるのに頭の整頓を必要とするからです。 会うたびに、バリ人の奇行動のおもしろさを語る人、 バリのヒンドゥー文化について分析する人、 バリ人についての文句しか言わない人、、 バリ人に見切りをつけてジャワ人を褒めたたえる人、、 とにかく、バリの慣習、文化、バリ人自体、、ってネタが尽きないんです。 そして、おもしろくもあり、魅力的でもあり、そしてストレスもたまることも。 だから、日本人の私たちがバリ島で渡り歩いて行くためには、 自分をしっかり持つことが大切。ちょっとした自分なりの解釈が必要です。 そして、バリ島について、わけが分からなくて身動きが取れなくなってしまっている方にも、ぜひとも、解釈を持って欲しいと思います。 生活の幅を広げるため、人生の楽しみを失わないため、現地での視野を拡げるため。。などなど。でしょうか。 バリヒンドゥーって、純粋なインドからやって来たヒンドゥーというより、 土着の信仰がまざりあってバリスタイルになった。と解釈する方が正しいかなと思います。 (私はヒンドゥーについて語る基盤は何も持って無いので、あくまで素人考えの域です。) 姜 尚中(カン サンジュン)さんによれば、(『悩む力』集英社新書) 近代の宗教のあり方に対し、かつての宗教のあり方として、 「かつての宗教は、人々が生きている世界そのもの、生活そのもの、もっと言えば、人々の人生と一体化したものでした。信仰を意味する「レリージョン(religion)」の語源はラテン語の「レリジオ(religio)」で、制度化された宗教というニュアンスがあります。つまり、宗教というのは「個人が信じるもの」ではなく、「個人が属している共同体が信じているもの」だったのです。」 と、あります。 「共同体の生き方」そのもの、ということですから、 自分1人の個という存在は共同体の中に埋もれているといえます。 そして、 「人が何を信じ、ものごとの意味をどう獲得するかという問題は、「信仰」によって覆い隠されていたとも言えます。」 とあります。 個々の意志による選択なのではなく、共同体の中で長年まもり続けられて来たルールによって個人のあり方も考え方さえも決められる。 実際のバリ人はどうかと言えば、たとえば、田舎の農家の高校生の生活を示してみましょう。 朝、神様にお供え物をして、ウシに食べさせる草を刈る、学校へ行く。 学校から帰ったら、またウシに食べさせる草を刈る、畑に行って農作物の収穫を手伝う。 セレモニーがある日は正装してお寺にお祈りに行く。 村の青年団の会合がある日もある。ここでは特別なセレモニーの役割分担や業務について話し合う。 もし、夕食が無かったら、自分で料理する。 セレモニーが無くても、自分の家の行事があれば、自分の家のお寺でお祈りをする。 学校でも特別なセレモニーの日には、正装して登校し、学校のお寺で全員でお祈りをする。 バスで大きなお寺に出かけてお祈りをすることもあります。 友達に会いたかったら、農作業が終わった後に道沿いに座る。 必ず誰かが通りかかるので、そこで話をする。 これは毎日のようにやります。これが楽しみの1つです。 もしくは、セレモニーでお寺にお祈りに行った時に出会えることが大変楽しい。 それが友達との遊びといえるかもしれません。 勉強をする時間はほとんど無い様です。 もちろん、田舎にはアルバイトの機会なんてありません。 生活のすべてがバリヒンドゥーと家の手伝いに終始している。 その合間に友達との交流がある。 大人、と言えば学校の時間の部分が農作業に変わり、セレモニーの機会は同じ、そしてさらに大人組の会合(バンジャールの会議)が毎日のようにある。 毎日宗教行事の準備に勤しみます。  高校生という視点で言えば、こういった生活の中で自己の意思決定をするというのは日本でも難しい。 そうではなく、大人のバリの人々も見ながら、私が思うのは、この共同体の慣習の中に従って生きていくことは、 個という単位で決めごとをする、という機会が日本のような個人判断をすべきことが多い国に比べて圧倒的に少ないのではないか、ということです。 実際のバリ人のモラルに基づく生活マナーは、日本の常識的マナーに比べて大変レベルが低いと思いますが、それでも、彼らに聞けば、行動とは裏腹に非常にきれいな倫理観を口にする。 人間のあり方、恋愛のあり方、結婚のあり方、善悪の判断、などなど、問うてみれば、尊敬に値する美しい考え方を教えてもらえます。 そして、彼らはその考え方を心の中に持ち(身に付いているとは思いませんが)共同体の中での教えに従って生きていくのです。 こういった生活スタイルが近代以前からずっと続いているのだと思います。 バリヒンドゥーの信仰の考え方に基づいた共同体の慣習の中にどっぷりと浸かって生きていくこと。 「これが正しい生き方」という価値観が形成されている。 ・個人の意見を言う、 ・自分の進路を見いだす、 ・自分で決断する、 という必要があまり無いのかな、と感じます。 というよりも、そうしたいが、できない。とも言えるでしょう。 だから、何か決めごとをしようとなると、日本人側はイライラする。 小学生の時に、何かをしようよ、という提案に、「お母さんに聞いてみないとわからない」 というスッテプが必ずあったと思います。 バリ人の人々の生活は、「バリヒンドゥーのカレンダーを確認してみないとわからない」「バンジャールの動きを確認してみないとわからない」 これがずっと死ぬまで続いているというような感じ。 南国の人々が時間にルーズである、ということは有名です。 もちろん、バリでも同じ。 けれどさらに、バリでは、この共同体内での価値観が考え方の中心となるものだから、 約束をしても、共同体内での急な用事があればこちらが優先される、キャンセルしても悪くない。 こういったことがしばしばだから、時間に遅れたって何の悪いことも無い。 自分は共同体の役割を果たしているのだから、正しい。 ということが加わり、余計にややこしくなる。 もし約束した相手が日本人だったら、時間にルーズなんてもんじゃない。誤りもしない!という怒りの事態が生じる。 でも、バリの人々は自分が悪い、なんてちっとも思っていないのです。 私は、バリ島にバリヒンドゥーがあることは、大変すばらしいと思っています。 そして、バリ島という存在を誇りにも思っている。 でも、こういったまったく異なる慣習の中で生活する人々との相互理解というものは、大変に難しく、苦労を必要とすることだと思います。 長く関われば関わるほど、ややこしい解釈が必要になる。 だから、自分なりの解釈、評価軸を持つ必要がある。 日本人の価値観に沿った判断基準を用いると、相手の民族としての人間性をも否定しかねないことだってあり得る。 そこを、日本人である私たちが、いかに幅広く捉え、受容し、学び、こちらからの意見も投げ、相互で成長していく必要があると思うのです。 バリ島で家をさがすには? どこに住む? バリ島でオススメの観光ー寺院ータマンアユン バリ島 観光はパックツアーか?個人ツアーか?どっちがいい? ウブド1日観光ツアーのイチ押しコース! バリ島旅行で失敗しないコツ! バリ島 旅行への忘れては困る 必需品!出発前にチェック! バリ島ーどこで 両替しますか? バリ島 バリ人の食事の仕方 バリ島 バリ人の大切な友達が病気 バリ島のカースト(身分)制度の現実は? バリ島 の病気 | |
Copyright (C)2007 Langit-Bali.com All
Rights Reserved.